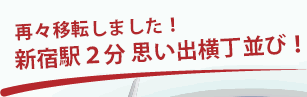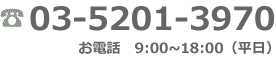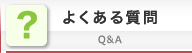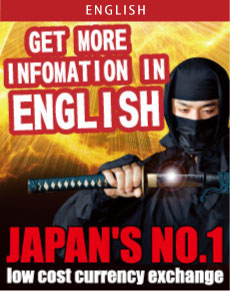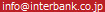0620 遅刻事件

2003年 証券会社の営業マン時代
ある日、目を覚ますと目覚まし時計があり得ない時間を指していた。どう考えても間に合わない遅刻の時間だったのである。やってしまった。言い訳にもならないが、私は家が遠いというのもあって何度か遅刻をしていたので、さすがに再三再四の遅刻はマズイと青ざめた。自己嫌悪に陥りながらも何も見出せない仕事に嫌気が差していたのもあって、半分どうでもよくなっていた。それでも上司が何とか納得する理由を考えてとにかく電話報告をしなくてはならない。焦って考え付いた案が体調を悪くして病院へ行っていることにするものだった。
悪知恵を働かせ、合理的なつじつまを合わせるために病院へ行ってそこの公衆電話から会社に連絡をとった。病院は携帯が使えないし社用電話にはしっかりと番号通知が出るため、不審に思われないよう取った行動であった。自分でも情けなく恥ずかしい行動にうんざりしていたが、その時は会社にばれないようにするために必死で取り繕っていた。欠勤や遅刻早退はしかるべき理由があってもなかなか認めてくれない厳しい風潮があったので、私は思わず会話の中で入院をしなければならなくなったと話したのである。
さすがに上司も驚いたようで早々に電話を切ることに成功したのだが、その後は一件落着とばかりに特に何をするでもなく平然と1日を過ごした。その日は金曜日だったが土曜日になって、さすがに入院は一大事なので退院したと告げるために部長の携帯に直接電話したが繋がらなかった。後で分かったことだが何かの間違いで違う番号が登録されていたのだった。だが、週末の日曜日に悪夢が待っていた。
欠勤をしたことは特に気にすることなく、不徳にも当時付き合っていた彼女と遊んで過ごしていた。そしてその最中に一本の電話がかかってきたのだ。「●●(部長の名前)だけど、今お前が入院している病院に来ているのだがお前どこにいるんだ?」その瞬間、私は背筋が凍りつき、全身の血の気がスーッと引いていくのを感じた。頭が真っ白になり絶句して一瞬、言葉が出てこなかった。まさか病院に来るとは。とてつもない緊張とパニックの中、全神経を張り巡らせても言い訳をするのは不可能だった。私は堪忍し、正直に真実を告げるしかないと思った。
何も知らずに見つめる彼女の前で、体が震えるような感覚があったが声だけは震えないように「すいません、入院はしていません。」と告げた。当然上司は説明を求めてきたのだが、その口調は次第に強く冷ややかな語気になっていった。「どういうことなんだ。」上司は入院したということが虚偽で私は無事であるということをその後確認しただけで「分かった」とだけいいながら電話を切った。その電話で一言謝罪をすることもできないほど短時間の会話だった。
電話を切り、固唾を飲み込んで一呼吸置くと自分が犯した愚行に凄まじい後悔の念と恐怖感が襲ってきた。私の異様な態度を察した彼女は、間髪いれずに尋ねてきた。錯乱している私にすぐに芝居をするほどの演技力などない。これほど情け無くて器の小さい男であることを決して知られたくは無い相手だったが、つい数ヶ月前に同じ職場を辞めていた彼女だったので、この恐怖心を少しでも和らげるためにも誰か事情が分かる人間に話して少しは楽になりたいと思った。
ありのままを話すと、案の定彼女は呆れていた。呆れながらも、深刻な表情をしている私とは対照的に普段どおりの振る舞いをしているその姿にのんきなものだと思いながらも少しは救われた。しかし週明け明日の出勤のことを考えるとそれは微々たる安堵感であった。私は気分が落ち込み、何をするにでも終始そのことが頭から離れなかった。
そして迎えた翌日の月曜日、これほど出社する足取りが重い日はないだろう。何度も深呼吸をして気持ちを落ち着かせながら会社へ向かったが、毎朝呼んでいる日経新聞も全く頭に入らないほど胸に大きな痞えがあるような心境だった。神妙な面持ちでオフィスに入ると真っ先にその部長に駆け寄り、謝罪をした。せめてもの礼儀だと思ったからだ。しかし、とりあえず座っていろと返され席についていたが恐らく支店長を始めた役職者、いやもしかしたら本店の全員が事情を知っているかもしれない、白眼視として背中に感じる視線はそれはもう痛い程だった。穴があったら入りたい、私のことを知ってか知らずか何気ない日常を送っている同僚達のほのぼのとした会話がとても遠くに感じられた。どんな罰でも甘んじて受け入れよう、刑の執行を待つさらし者の囚人のような気分であった。
一連の朝礼が終わった後に、その部長にオフィスの片隅にあるミーティング室に呼び出された。とうとう来た、予測をしていたので私はせめてもの反省の念から速やかにそこへ入室した。部長は腕を組み、私と対峙して座りながら開口一番「どいういうつもりなんだ」と問い詰めてきた。週一回の休日にも関わらず、彼の自宅から3県も離れている私の地元まで見舞いに来てくれていたらしい。それが嘘だということが分かり引き返すときの気持ちは如何ほどだっただろうか。実際にそれについては平身低頭ただ謝るしかなかった。100%自分が悪い、弁解の余地が無いのは明らかだった。
そして私に対する追求は普段の仕事に対して及んだ。やはり部長は、成績不振も甚だしい身分でありながらこのような不祥事を起こしたことに憤慨していたのである。確かにそこで猛省をして明日から心を入れ替え努力しますという月並みな返答をすれば立場上部長も個人的な怒りや感情は別にして許さざるを得ないだろうし、私もそうするしか手立てがないだろうという立場であると思われていたに違いなかった。
しかし、私の中にこの仕事に対して半ば諦めのような、悲しいかなどういうきっかけがあるにせよ挽回できるほどの見込みはないと実感していたのだった。当然、認めたくは無いし悔しいし、残念ではあるが本当にもうお手上げ状態、白旗であった。ここで本意ではない意思を告げて、また元の木阿弥、出口の無い迷路に再び舞い戻ることはとても受け入れがたかった。大変な迷惑をかけた申し訳無さを痛感しながらも自分の真意つまり、この仕事を続けるのが困難であると告げることが出来ずにしばらく沈黙するしかなかった。
私は下を向いてうつむきながら、塩をかけられたナメクジのように小さくなりうなだれていた。痺れを切らしたのだろうか、突然部長が「何とか言えっ!」と怒鳴り、私を一喝したのだ。天敵に威嚇された小動物のように本能的にびくっとしたのと、責任を感じて小さく畏まっていた私は危機迫るものを感じてひどく驚き、捨て犬のような今にも泣き出しそうな怯えた目で部長を見返してしまったのである。
恥辱ここに極まれりという感じであった。面子や面目といった私の男としての最低限の尊厳すら木っ端微塵に跡形無く消滅していた。焼け野原で敗戦の玉音放送を聞いているあのやるせない情景と重なるものがあった。重い口を開き、自分の思いを告白した。部長、そして会社は決して私を辞めさせようとしている訳ではなかった。ただ、もうこれ以上続ける自信がありませんと降参を宣言する私に、想定していたのだろうか部長は険しい表情を変えることなく、ここで何の成果も出さずに諦めるのか、もう一度頑張る気持ちは無いのかと諭してくれた。だが、その発言は引き留めようという意思からくるものではなく、あくまで一人の営業マンとして彼自身の哲学と仕事に対する誇りからくる、本当にそれでいいのかという率直な問いかけであったのだと思う。
ノックアウトされたボクサーのように、私にはもう一度立ちあがりファイティングポーズをとる気力も自信もあるはずがなかった。部長は部屋を出て行き支店長が入ってきた。一連の事情を説明するように言われてから、部長と同じく再び私の進退の意志について問われた。大変お世話になり慕っていた上司ではあったが、既に打ちのめされていた私は断腸の思いで自身の限界を吐露するしかなかった。社会人としてあるまじき行動をとりながら、その責任を今後の仕事で挽回しようという気持ちすらない私を、彼らの価値観が僅かでも肯定するはずが無かった。
苛立った様子で「やめちまえ。」そうはき捨てて部屋を出て行ってしまった。その言葉が胸に突き刺さり、本当に切なかった。今まで営業部は個々の成績には厳しくとも組織としては家族のように暖かい人間関係を感じていた。その組織を統率する支店長は大黒柱で中心人物のような存在の人だったからだ。
完全に見放されてしまった。この一年間、苦しい時間が大半だったが時には笑顔で共に働ける仲間でいることを自慢に思える絆があると思っていたのに。急に手のひらを返され、部外者として外に放り出されたような疎外感を感じた。自分がしたことはそれほど悪いこと因果応報なんだと思うしかなかった。辞職が確定的になり、私の気持ちもこの場から去るべきと覚悟を固めていった。しかし今後の当てなど何もない。他の企業に就職するということももちろん、こんな不和を残したままの結末で新卒の会社に幕を下ろすなど受け入れがたいという気持ちに後髪をひっぱられる思いで一杯だった。
だが、営業が出来ない人間が営業の会社にいる存在意義などない。落ち武者が都落ちする気分で荷物をまとめにかかろうとした時、最後に役員である統括部長から声がかかった。私の事情は既に耳に入っていたらしく、一連の出来事については特に触れられることはなかったが私の辞意に関してはそれを受け止めた上で、他の部署が人員を必要としているのでそこの担当部長と話してみないかと言われた。